お急ぎの方はお電話にて
050-3562-4237
お急ぎの方はお電話にて
050-3562-4237

日本語通訳とは、日本語と他言語のペアで行う通訳を指します。
日本語⇔英語、日本語⇔フランス語、日本語⇔中国語など、言語ペアは多岐に渡りますが、日本語を扱う通訳はすべて「日本語通訳」と呼ばれます。
プロの日本語通訳者は、世界的に不足しています。
それはなぜでしょうか。
日本語通訳者は、世界的に需要が高いにもかかわらず、供給が不足しています。
日本は経済大国であり、海外とのビジネス取引が盛んです。
しかし、日本人は一般的に英語が得意でないため、通訳者を介したコミュニケーションが必要とされます。
一方で、通訳者の供給は需要に追いついていません。
日本語は日本国内でしか広く使われず、また習得難易度の高い言語のひとつです。
3種類の文字(ひらがな、カタカナ、漢字)を使い分け、複雑な文法体系を持つため、外国人が通訳レベルまで到達するのは容易ではありません。
その結果、日本語通訳者の多くは日本人(日本語ネイティブ)です。
例として、日本でトップクラスの通訳者が所属する「日本会議通訳者協会」の認定会員は、90%以上が日本人で占められています。※脚注11

日本語通訳は、他の言語にはない独特の難しさがあります。
それは、「語順の違い」です。
中学校の英語の授業で習うことですが、日本語の文法はSOV型、それに対して英語はSVO型です。
S=主語、O=目的語、V=動詞
| S | V | O | |
| 日本語 | 彼は | 書類を | 破棄した |
| 対訳 | He | the document | discarded |
| S | O | V | |
| 英語 | He | discarded | the document |
| 対訳 | 彼は | 破棄した | 書類を |
上記の通り、日本語と英語では、OとVの順序が逆になります。
従って、通訳者は「OとVを入れ替えるパズル」を常に強いられ、通訳時の大きな負担となります。
上の例文「彼は・書類を・破棄した」の場合、文が短いので単純なパズルで済みますが、文が長くなると難易度は一気に上がります。
以下の文を見てみましょう。
| S | V | O | |
| 日本語 | 彼は | 二週間前に部長のデスクにあった青いファイルの書類を | 破棄した |
| 対訳 | He | the document which was placed on the manager’s desk two weeks ago | discarded |
通訳者は正確な訳出を目指して最大限の努力をしますが、全ての情報を網羅することは難しい場合があります。
そのため、通訳者はこのような文に直面したときに「絶対に落としてはいけない情報」と「落としても致命的ではない情報」を瞬時に仕分け、優先的に訳出します。
この文章における重要なキーワードは、「彼は」「書類を」「破棄した」の3点です。
これらの情報は文の中心であり、正確な訳出には不可欠です。
一方、「二週間前に」「部長のデスクにあった」「青いファイルの」などは補足的な情報であり、重要性は低くなります。
重要なキーワードを落とすと致命的な誤訳につながるため、通訳者は常に高い集中力を保たなければなりません。
通訳者は、単に聞いた言葉を右から左へ変換しているわけではありません。
話の意図を理解し、自然な訳出を行うために、常に話の流れを予測しながら頭の中で情報を処理します。
英語のように重要な情報が文頭に来る場合は、話の方向性を見つけやすいですが、日本語では重要な情報が文末に来ることが多いため、通訳者は文が終わるまでその意図を把握しにくいのです。
この語順の特性は通訳者にとって大きな障壁となり、話の流れが見えない状態で訳出することは、霧の中を地図なしで航海するような不安を伴うのです。
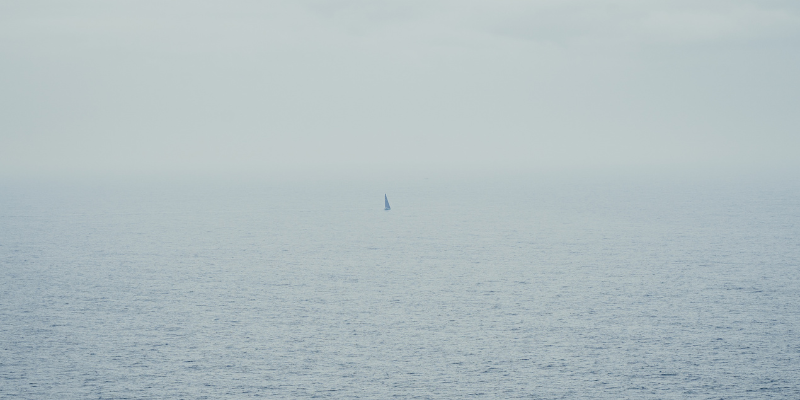
世界の主要言語のほとんどはSVO型です。
英語、フランス語、スペイン語、中国語、ロシア語など、国際的な取引や海外ビジネスの場で使われる言語の多くがSVO型を採用しています。
一方、日本語は少数派のSOV型に属します。
そのため、日本語とペアになる通訳の多くはSVO型との組み合わせとなり、日本語通訳者は「OとVを入れ替えるパズル」を常に解かされることになります。
この語順の違いこそが、日本語通訳の難易度を大きく押し上げている要因の一つです。
このような理由から、日本語通訳は他言語間の通訳に比べて難易度が高く、日本語通訳者は慢性的に不足しています。
特に、日本語非ネイティブにとっては、実に狭き門の職業です。
しかし、これは裏を返せば「日本語ネイティブにとって大きなチャンスが広がっている」とも言えます。
少子化により日本語ネイティブの人口は確実に減少するなか、優秀な日本語通訳者は希少価値を持ち、国際ビジネスの場で高く評価されることでしょう。
もちろん、日本語ネイティブにとっても、プロの通訳者として活動していく道は平坦ではありません。
それでも、日本の未来を支える一つの柱として、より多くの人が「通訳」という職業に挑戦してくれることを願っています。
INTERPは「通訳育成プログラム」を提供し、日本語通訳者を目指すすべての人に広く門戸を開いています。
実践的な通訳スキルの指導だけでなく、他国のビジネス慣習の理解やキャリア構築のアドバイスに注力し、世界的に不足している日本語通訳者の供給を増やすべく取り組んでいます。
INTERP合同会社代表。株式会社 S.H.C. Collaborationグローバル教育社外顧問。横浜市と米国ダラスで幼少期を過ごす。家族との時間とワークライフバランスを大切にするため、現在はマルタ共和国を拠点にリモートで経営を行っている。
2011年より通訳者として活動を開始し、現在は国際イベントと人材育成に注力。海外ビジネスの円滑化を支援するため、セミナーや情報発信にも積極的に取り組んでいる。


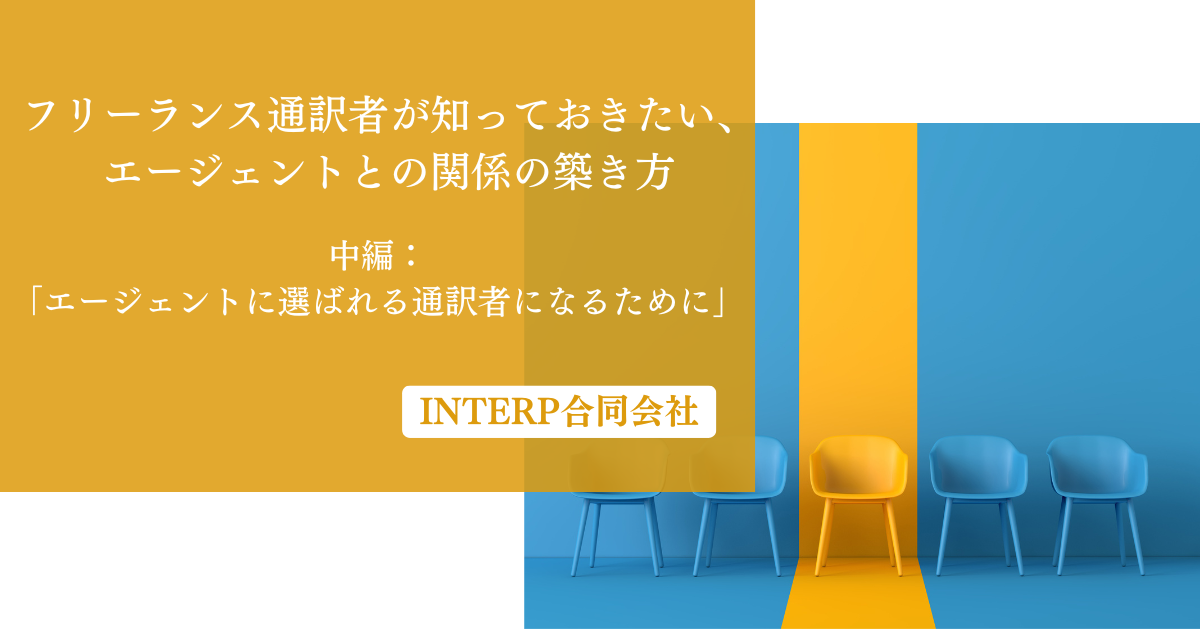
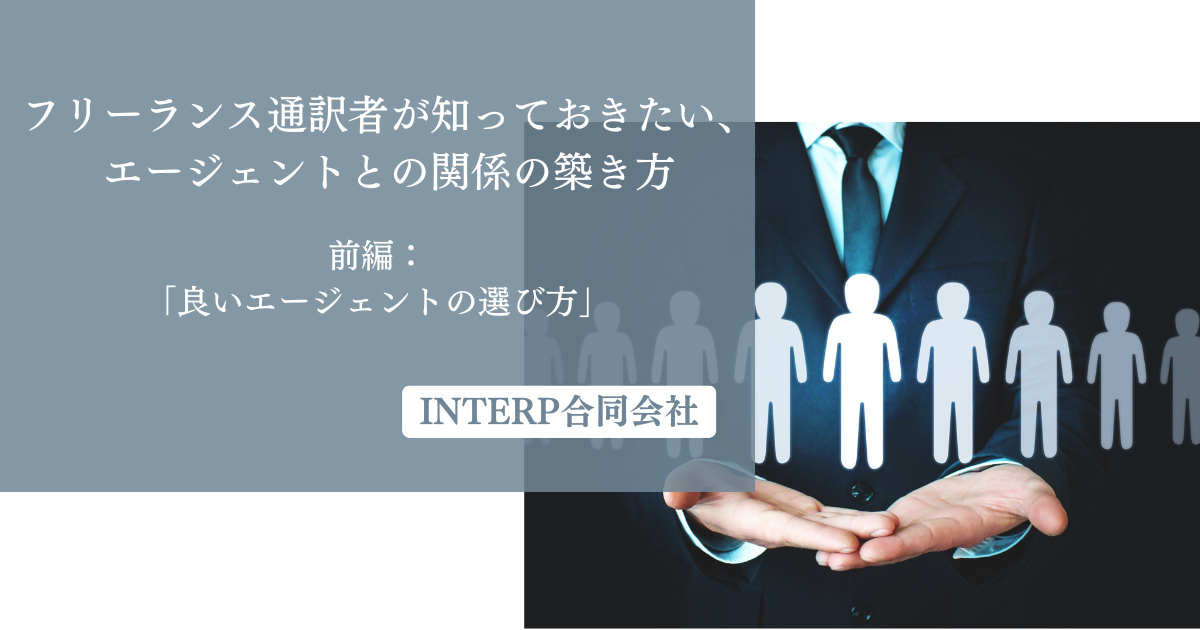
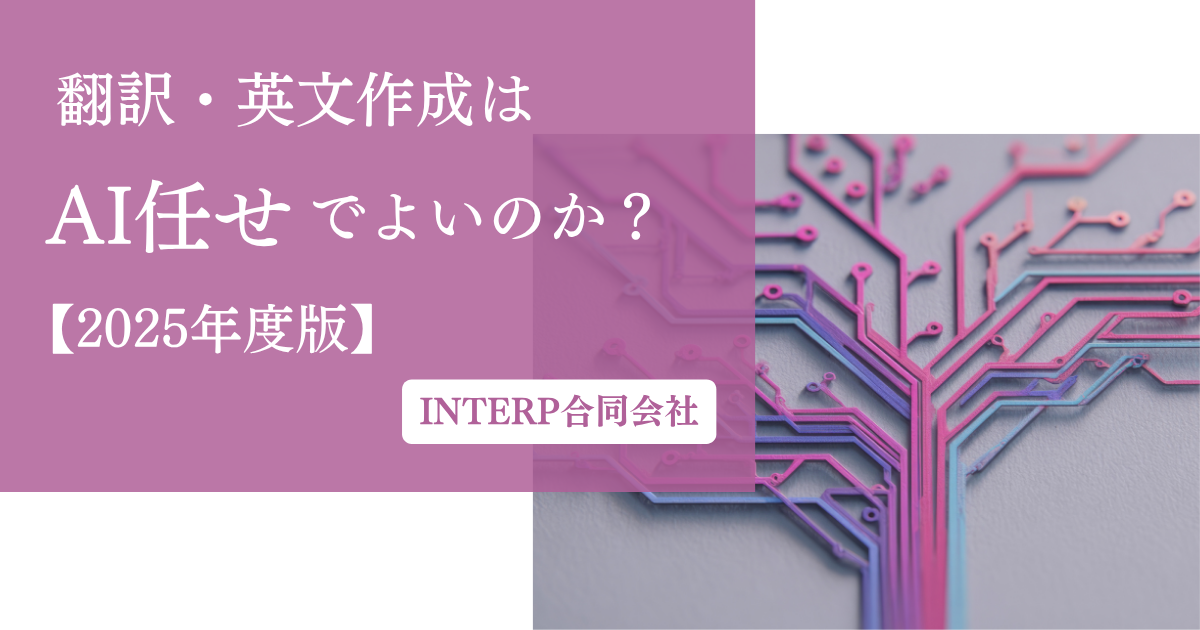
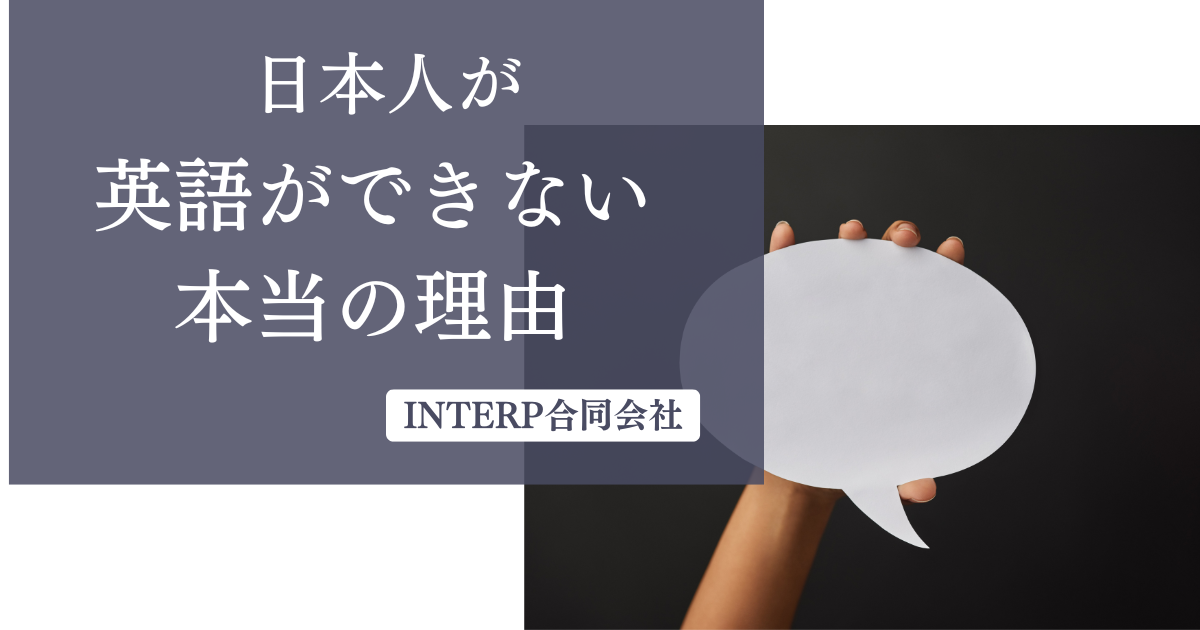

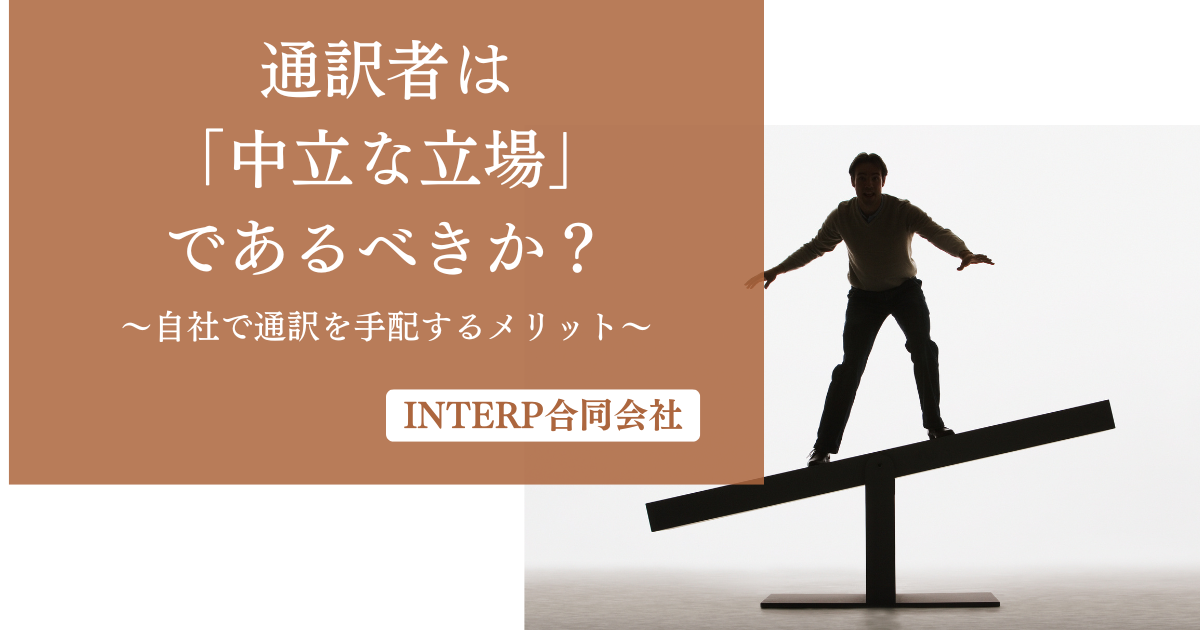
お急ぎの方はお電話にて
050-3562-4237
(受付時間 / 平日9:00 - 18:00)